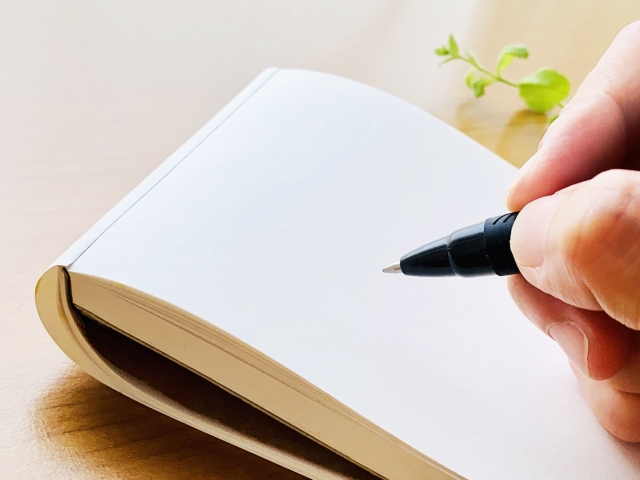俳句を作る際には、それぞれの季節を代表する「季語」を使うことが一般的です。自然や文化を題材にすることで、作品に深みを持たせることができます。
このガイドでは、1月から12月までの各月にぴったりの季語を簡潔に紹介しています。
これを使って、季節を感じる俳句を作る挑戦をしてみましょう。
特に小学生のみなさんは、休暇の間にこのガイドを利用して、俳句の宿題に役立ててください。
俳句の季語について
俳句で使われる「季語」は、特定の季節を象徴する言葉です。これらは長い間、日本の文化に深く根ざし、自然の変化や季節の節目を詩的に表現するために用いられてきました。
季語は次のように分類されます:
- 春の季語:立春から立夏の前日まで
- 夏の季語:立夏から立秋の前日まで
- 秋の季語:立秋から立冬の前日まで
- 冬の季語:立冬から立春の前日まで
- 新年の季語:1月1日から1月15日まで
新年の季語は新年を祝う特別なカテゴリで、季節ごとの季語は日本の二十四節気に基づいています。詳しく知りたい方は、「歳時記」という専門書を図書館や書店で探してみると良いでしょう。
季語と季節のずれについて
俳句の季語は季節感を表現する上で重要ですが、新暦(グレゴリオ暦)と旧暦の違いによる季節のずれに注意が必要です。新暦は太陽の周期に基づくのに対し、旧暦は月の周期に基づいています。これにより、季節感に約1ヶ月のずれが生じることがあります。
以下は新旧暦での季節の区分です:
- 旧暦の季節:春は1月〜3月、夏は4月〜6月、秋は7月〜9月、冬は10月〜12月
- 新暦の季節:春は2月〜4月、夏は5月〜7月、秋は8月〜10月、冬は11月〜1月
気象学的な季節は一ヶ月ずれており、日本が海洋性気候であり、中国の大陸性気候と異なるため季節感がずれます。季語を選ぶ際にはこれらの違いを理解し、考慮することが大切です。
旧暦と新暦での季語の使い分け
季語は、それが起源とする暦によって使い方が異なります。この章では、どの季語を旧暦に基づいて使うべきか、どの季語を新暦に合わせるべきかを説明します。
旧暦に基づく季語の使用方法
旧暦で行われる行事に関連する季語は、旧暦の月に合わせて使います。例えば、「七夕」は旧暦7月の行事で、新暦では夏から秋にかけての時期になります。そのため、七夕を新暦の7月ではなく、秋の季語として考えるのが適切です。
また、「十五夜」は旧暦8月15日に行われるため、新暦では9月から10月にかけてとなりますが、これも旧暦に基づいた季節である秋の季語として取り扱います。
新暦に基づく季語の使用方法
新暦で始まった行事は、新暦の月を基準に季語を選びます。たとえば、「バレンタインデー」は新暦の2月14日に固定されており、この月は新暦の春の季語に該当します。「ハロウィン」も10月31日が行事日で、新暦の秋の季語になります。
旧暦で始まった行事は新暦で表現する場合でも、旧暦の季節感を尊重することが大切ですし、新暦で始まった行事は新暦の季節区分を適用します。
季語を適切に使用するためには、その行事の暦の起源を理解することが重要です。歳時記を参照することで、季語と季節の関係を正しく把握し、俳句作りに活かすことができます。
必見:小学生向け季節別俳句季語リスト
俳句を作る上で欠かせない「季語」を新暦に基づいて月別に整理し、小学生にもわかりやすく紹介します。これを使って、俳句作りをより楽しく感じることができるでしょう。
春の季語
期間:2月4日から5月5日(立春から立夏前日まで)
カテゴリ:自然、動物、風景
季語の例:
自然:クレソン、芽吹く木、スミレ、菜の花
動物:カエル、雲雀、蜂
風景:春分の日、春の夕日
夏の季語
期間:5月6日から8月7日(立夏から立秋前日まで)
カテゴリ:自然、動物、風景
季語の例:
自然:夏野菜、セリ、ワカメ
動物:おたまじゃくし、蝶
風景:風船、夏の光
秋の季語
期間:8月8日から11月7日(立秋から立冬前日まで)
カテゴリ:自然、動物、風景
季語の例:
自然:紅葉、秋桃、ロウバイ
動物:山鳥、ウグイス
風景:節分、旧正月
冬の季語
期間:11月8日から2月3日(立冬から立春前日まで)
カテゴリ:自然、動物、風景
季語の例:
自然:クロッカス、ハコベ
動物:雀、凧
風景:建国記念日、学校試験
これらを参考にして、それぞれの月や行事に合った季語を選び、季節の雰囲気に合わせた俳句を作ってみてください。このリストを活用することで、季節の移り変わりを俳句を通じて深く感じることができます。
春の季節に使える季語ガイド:小学生向け
春は俳句を作るのに豊富な季語があります。ここでは、「植物」、「動物」、「イベントや日常」のカテゴリごとに春の季語を紹介します。
春の季節全体での季語(2月4日〜5月6日)
植物:クレソン、伊予柑、新芽、シクラメン、ジンチョウゲ、スミレ、ナズナ、セリ、ワカメ
動物:アサリ、カエル、ヒバリ、蜂、蝶
イベント/日常:おぼろ月夜、春の訪れ、風船、春の夕日
2月の季語
植物:梅、桃、クロッカス、ハコベ、ミモザ、ツバキ、ロウバイ
動物:サヨリ、ウグイス
イベント/日常:天皇誕生日、春分の日、立春、バレンタインデー、旧正月、雪まつり、建国記念の日、入試
3月の季語
植物:桜、夜桜、つくし、タンポポ、若葉、菜の花
動物:ウグイス、ツバメ、蛤
イベント/日常:卒業式、ひな祭り、桃の節句、春分の日、花見、春休み
4月の季語
植物:桜、夜桜、筍、菜の花、チューリップ、アスパラガス、ハナミズキ
動物:鰆、ムツゴロウ、いかなご
イベント/日常:入学式、新入生、イースター、エイプリルフール、昭和の日、花見
これを参考にして、春の各月に合わせた俳句を作り、季節の感じを豊かに表現してみましょう。
夏季に適した俳句の季語リスト:小学生向け
夏の季節は5月6日から8月7日まで(立夏から立秋の前日まで)にわたり、この期間に使用する季語を「植物」、「生物」、「イベントや日常生活」のカテゴリーで紹介します。
夏の期間全体の季語(5月6日〜8月7日)
植物:青葉、パパイヤ、パセリ、ベゴニア、ペチュニア、日々草、夏ミカン
生物:アジ、アナゴ、アマガエル、鮎、蟻、蟻地獄、イモリ、蚊、蜘蛛の子、蚊蝋、ホタテ、ヤマメ、タコ、金魚
イベント/日常生活:雷鳴、アイスクリーム、半ズボン、サイダー、風鈴、ラムネ、水羊羹、夏風邪、水遊び、冷麦、そうめん、扇風機、夏の日々
5月の季語
植物:カーネーション、新緑、バラ、牡丹、竹の子、紫陽花、菖蒲、アヤメ、ルピナス、木いちご、バナナ、イチゴ、キウイ
生物:子猫、初鰹、巣立ちの小鳥
イベント/日常生活:八十八夜、立夏、端午の節句、こどもの日、母の日、田植え、初夏、鯉のぼり、かしわ餅、緑の日、新茶の季節、皐月
6月の季語
植物:紫陽花、玉ねぎ、びわ、アイリス、ラベンダー、ガーベラ、アマリリス、葵、どくだみ、ミョウガ、菖蒲、青梅、小梅、若竹
生物:カタツムリ、ホタル、牛蛙、ナマズ
イベント/日常生活:田植え、父の日、夏至、梅雨、梅雨入り、梅雨空、初夏の晴れ間、六月雨
7月の季語
植物:茄子、トマト、ピーマン、ゴーヤ、キュウリ、パイナップル、西瓜、月見草、グラジオラス、朝顔、向日葵、蓮、ダリア、メロン
生物:セミ、金魚、カブトムシ、クワガタ、テントウムシ
イベント/日常生活:梅雨明け、土用、入道雲、夏休み、花火、プールでの遊び、晩夏、浴衣の季節、夏祭り、熱帯夜、冷夏、炎天下、キャンプ、海水浴、林間学校、山開き、日傘、水着、うちわ、扇子、そうめん楽しみ、水鉄砲、浮き輪、風鈴、蚊取り線香、ゲリラ豪雨、かき氷、エアコンの涼しさを感じる日々
これらの季語を活用して、夏の俳句作りをさらに楽しむことができ、季節感を表現することができます。
秋季におすすめの俳句季語一覧
秋の期間、8月7日から11月7日まで(立秋から立冬の前日まで)に使用できる季語を、「植物」、「生物」、「イベントと日常生活」のカテゴリーに分けて紹介します。
秋の全期間にわたる季語(8月7日~11月7日)
植物:オクラ、稲、サツマイモ、梨、菊、シイタケ、生姜、ヘチマ、唐辛子
生物:カマキリ、ムクドリ、鹿、サケ、啄木鳥、シギ、トンボ
イベントと日常生活:秋の訪れ、長い夜、秋祭り
8月の季語
植物:スイカ、朝顔、桃、枝豆、ホオズキ、トウモロコシ、ナス、トマト、ピーマン、ゴーヤ、キュウリ、サルビア、桔梗、山椒の実、ナデシコ、向日葵、梨、葡萄、オクラ
生物:イワシ、タチウオ、芋虫、ヒグラシ、チャタテムシ、イナゴ
イベントと日常生活:花火大会、立秋、お盆、盆踊り、夏休みの終わり、終戦記念日、広島・長崎原爆の日、入道雲、初秋、浴衣、夕立、熱帯夜、七夕、天の川、残暑、夏の行事、風鈴、蚊取り線香、扇風機、エアコン、かき氷
9月の季語
植物:葡萄、巨峰、マスカット、秋ナス、コスモス、彼岸花、梨、新米
生物:スズムシ、コオロギ、キリギリス、マツムシ、赤トンボ、サンマ、サケ
イベントと日常生活:台風、十五夜、十六夜、敬老の日、防災の日、中秋、秋彼岸
10月の季語
植物:木の実、紅葉、キンモクセイ、新米、柿、イチジク、マツタケ、栗、松ぼっくり、どんぐり、コスモス、小豆、銀杏、カボチャ、サツマイモ
生物:渡り鳥、モズ、イノシシ、サンマ
イベントと日常生活:稲刈り、秋晴れ、運動会、文化祭、晩秋、スポーツの日、ハロウィン、台風、紅葉狩り
これらの季語を使って、秋の風景を色鮮やかに表現する俳句を楽しんでください。
冬季に活用できる俳句の季語リスト
冬の期間、11月7日から2月4日まで(立冬から立春の前日まで)の間に使用できる季語を「植物」、「生物」、「イベントや日常」のカテゴリーに分けて紹介します。
冬の全期間の季語(11月7日~2月4日)
植物:カブ、ブロッコリー、セロリ、大根、キャベツ、白菜
生物:アマダイ、ズワイガニ、フクロウ、カキ、ブリ、タラ、鯨、鱈、冬眠する動物たち
イベントや日常:冬の寒さ、北風、空風、霜、毛布、おでん、冬帽子、火鉢、ストーブ、こたつ、暖炉、オリオン座、重ね着、風邪、セーター
11月の季語
植物:サザンカ、松ぼっくり、どんぐり
生物:シシャモ、ワタムシ、初鱈
イベントや日常:七五三、初冬感、立冬、小春日和、木枯らし、霜柱、十一月、霜月、初霜
12月の季語
植物:ミカン、ポインセチア、クリスマスローズ
生物:白鳥、鶴、初ブリ
イベントや日常:クリスマス、冬休み、冬至、年末、大晦日、仲冬、スキー、初雪、スケート、氷柱、雪だるま、雪合戦、霜柱、師走、除夜の鐘、雪遊び、大掃除、寒中水泳
1月の季語
植物:水仙、ツバキ、七草、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、若菜、福寿草
生物:寒ブリ、寒シジミ
イベントや日常:新年、元日、正月、三が日、初詣、初笑い、雪景色、鏡開き、お年玉、晩冬、氷柱、雪だるま、雪合戦、書き初め、新春、初日の出、雑煮、門松、一月、睦月、すごろく、初夢、羽根つき、寒中水泳、成人式、成人の日、三寒四温
新年の季語
新年の期間は1月1日から1月15日までです。この短い期間に使える季語をまとめます。
植物:七草、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、若菜、福寿草
生物:伊勢エビ、数の子
イベントや日常:新年、元日、正月、三が日、初詣、初笑い、お餅、鏡餅、鏡開き、お年玉、新春、初春、初日の出、雑煮、門松、一月、すごろく、初夢、羽根つき、凧揚げ、コマ回し、初売り
これらの季語を活用して、冬の季節の特徴や美しさを表現する俳句を創作してみましょう。季語の選択が俳句の魅力を深め、季節の感覚を豊かにします。また、新しい季語も増えているため、最新の情報を得るために歳時記を参照するのがおすすめです。
まとめ
ここでは、季節ごとの俳句作成に適した季語を紹介しました。春、夏、秋、冬それぞれの期間に分類される季語を「植物」、「生物」、「イベントや日常」というカテゴリーで整理し、季節の特色を捉えた俳句作りの手助けをします。
例えば、春には「桜」や「ウグイス」、夏には「蝉」や「花火」、秋には「紅葉」や「サンマ」、冬には「雪だるま」や「おでん」といった季語が季節感を表現します。これらの季語を使うことで、四季の移ろいを感じさせる豊かな表現が可能になります。
それぞれの季節に特有の自然や文化の象徴を詠み込むことで、俳句が一層魅力的になります。